俳優とは、ペルソナである。
SCT新作映画『HALF』脚本担当の中井由梨子(mosaique-Tokyo)です!
二ヶ月半にわたるワークショップも折り返し地点に差し掛かっています。2021年新作予定の『HALF』のスケッチを書く筆が最近のってきて、ついには人間じゃない登場人物まで出てきました(笑)
初回は緊張で固い表情だった受講生の皆さんも、今ではとても自然に、そのままの自分で芝居に入っている気がします。
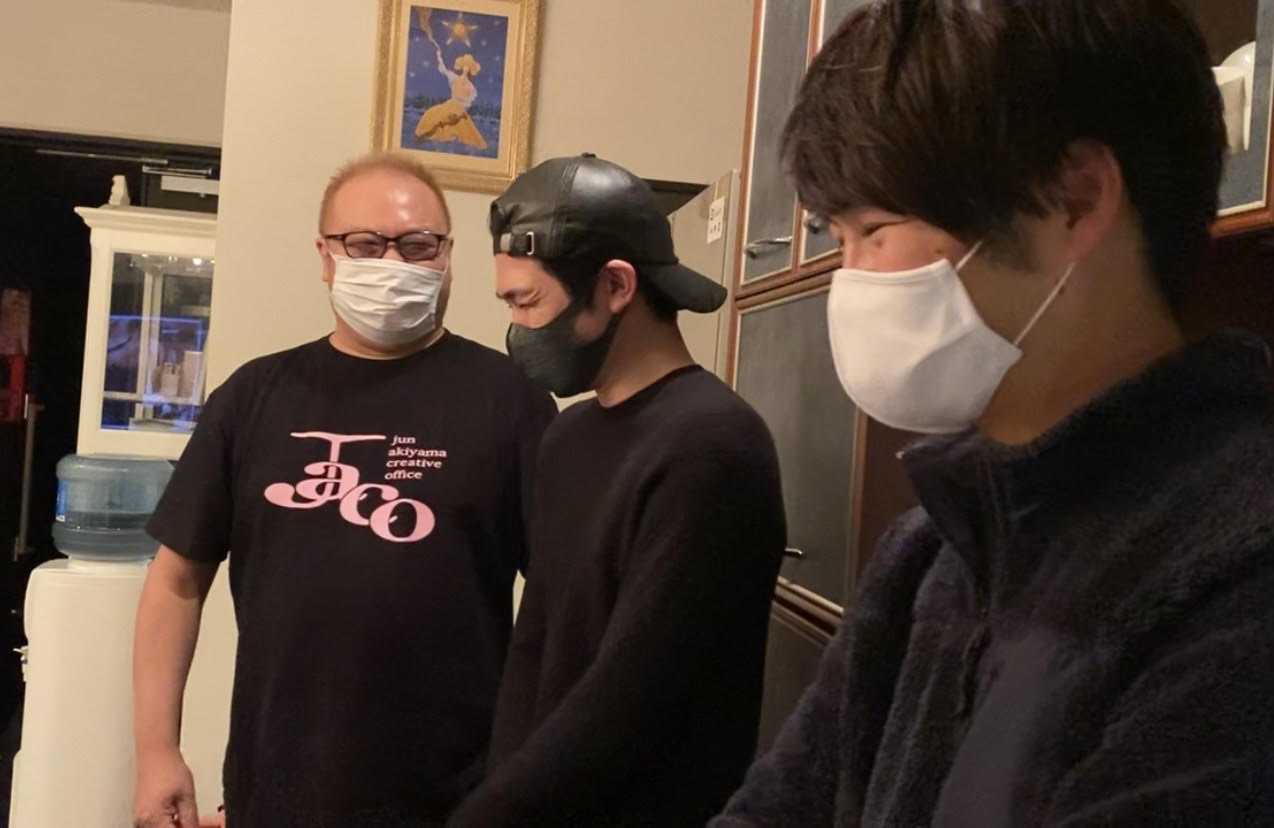
写真左から)秋山純監督・橋谷拓玖さん・吉木遼さん
「そのままの自分で」
もっとも簡単で、もっとも難しいことかもしれない。
人前で、カメラ前で”そのまま”なんて言われても出来るわけがない。普通でいれることなんてできないし、そもそもカメラ前なんていう状況が”普通じゃない”。俳優は、そんな普通じゃない状況で「普通」であれと求められる特殊な技能を必要とします。
ここまでやってきて、少しずつ着実に変わっていく皆さんを見ていて思うことは。
俳優とは、見た目や技術は(極端な言い方をすれば…)おまけ。そういったものではなく、
「在り方」が問われる職業である。
ということ。
人と人とが近づけず、生きづらさを伴ったご時世、俳優に限らず、芸能の分野で生きる人間すべてに「自分はどう在るか」が深く問われている昨今であることも否めません。

写真左から)松浦正太郎さん・杉山宗賢さん

写真左から)沖﨑健司さん・杉山宗賢さん
ちょうどそんなことを考えている時に、今回のワークショップでテキストとなっている本の著者、ブレッソン監督の映画が新宿で公開されました。
ロベール・ブレッソン監督作『バルタザールどこへ行く』『少女ムシェット』(新宿シネマカリテ)
http://qualite.musashino-k.jp/news/10970/


なぜブレッソン監督が俳優たちを俳優と呼ばず、「モデル」と呼んだのか。
昔から舞台芸術の世界でも教えられてきた「俳優とはペルソナである」という言葉が思い起こされます。演劇という名の芸術の主役は演じ手ではなく観客(視聴者)であるという考え方。俳優は観客の心情を写し出すペルソナ(仮面)であれ、という教え。
頭では理解していても、俳優も生身の人間。簡単に仮面になることはできません。
だからこそ、少しずつ実践を重ねて、「演じるな。存在せよ」の奥義を身に着けていくのだと思います。
演劇も映画も、表面的に見れば一番目立つのは俳優。けれど、その主役は俳優ではなく見えない観客である、という捉え方は物事の本質を見極める目と共に、「なぜ演劇を創るのか」というクリエイターの身をも顧みることができそうです。

写真左から)吉木遼さん・橋谷拓玖さん・安楽楓さん・小貫莉奈さん・福岡瑠璃さん
今回のシーンは、主人公のミナミが、家に突然現れた少年の面倒を見るため、慌てて職場から早退しようとするシーン。すでに月末で退職予定のミナミ。ミナミの恋人である周作が、実はミナミの上司の野渡丘と親友だった、という新しい情報を視聴者に伝えるシーンでもあります。この何気ない日常会話の応酬のシーンでの肝は何か。
自分は、どう在るのか。

ミナミ(小貫さん)は野渡丘(吉木さん)に書類を渡して早退しようとしますが…

野渡丘(吉木さん)はミナミの退職を認めたくないので話がしたい…

そこへミナミ宛てに顧客からの電話。野渡丘は足止めを食らったミナミをさらに引き留めようとするがあっさり逃げられる。
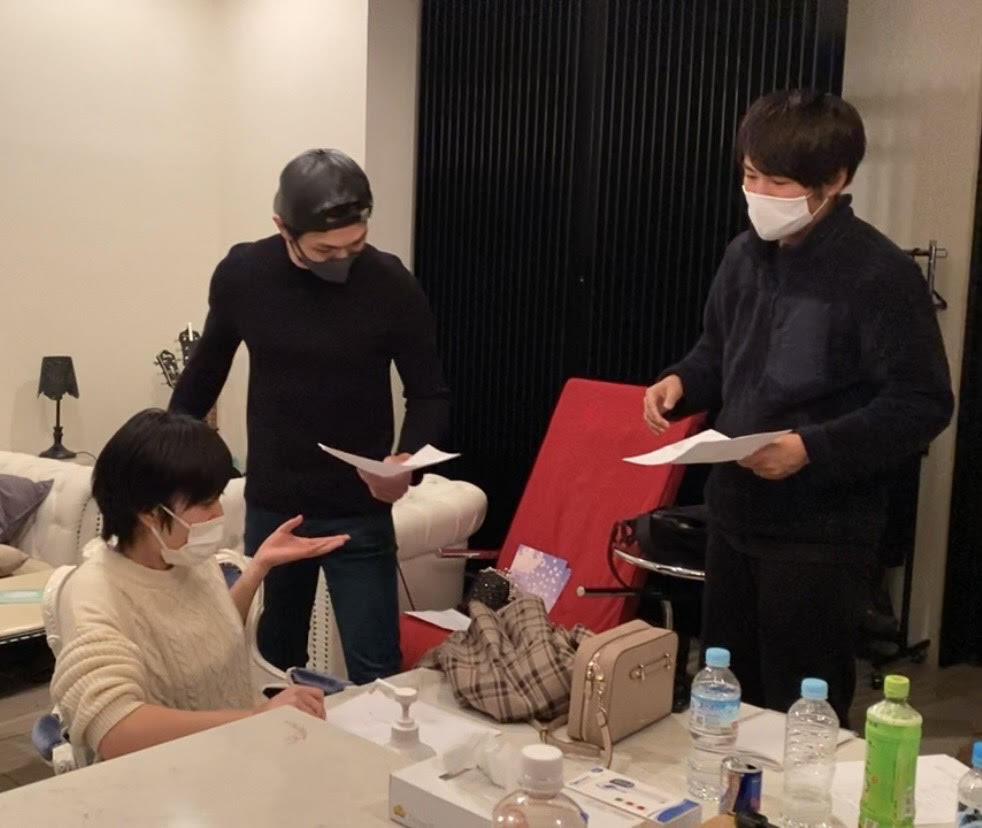
そこへ親友の周作(橋谷さん)が現れて…

野渡丘はミナミを辞めさせないためにはどうすれば良いかを周作に相談する…とても何気ないシーンです。
大事なことは、関係性のバランス。
”親友”である設定、というのは簡単なようですが、本当に視聴者がそう感じるように在れるか、ということに無頓着であってはならないのです。
俳優同士が同い年でも上下関係があるように見えたり、信頼関係が透けてみえてしまったり。逆を言えば、今日初めて会った俳優同士でも十年来の親友であることを信じさせてしまうことも可能なのです。では、その違いはどこにあるのか?
考察は、なるべく皆でシェアします。
画面左から)松谷鷹也さん・松浦正太郎さん・沖﨑健司さん・杉山宗賢さん・福岡瑠璃さん
観客(視聴者)は、それぞれの思い込みや思考を持ってドラマを見ます。
私たち創り手や俳優は、人に自分の芝居を見せようとするとき、
「真っ白なキャンバスに絵を描いているわけではない」
ことを常に念頭に置いておく必要があります。
絵を描こうとすればそれは、すでに赤や青や緑や黄色や、七色やいろんな模様や風景や人物がびっしりと描き込まれた、もしかしたら真っ黒に塗りつぶされたキャンバスに絵を描くことにもなるからです。
だから、裏を返せば、絵を描くこと自体が、意味を成さないことを知る必要がある。
逆なのです。
私たちこそが、真っ白なキャンバスを差し出す。
それが演劇の真髄であると思います。
第6回へ続きます!!



